日本の定番料理「きつねうどん」
寒い日に食べたくなる、やさしい味わいの「きつねうどん」。だしの効いた温かいうどんに、甘く煮た油揚げがちょこんと乗ったこの一杯は、昔から多くの人に親しまれてきました。でも、ちょっと気になりませんか?なぜ「きつね」うどんと呼ばれているのか…なぜ「油揚げ」なのか…。気になりますよね。
きつねうどんの由来

甘く煮た油揚げをのせたきつねうどん。その名前の由来には、いくつか説があります。
ひとつは、昔の人々が「油揚げはきつねの大好物」と信じていたことに由来する説。きつねは商売繁盛の象徴ともされていたので、縁起を担いで名づけられたと言われています。
もうひとつの説では、油揚げの見た目がきつねの毛色に似ていることから、「きつねうどん」と呼ばれるようになったとも言われています。茶色くこんがりとした油揚げが、ふと見るときつねの姿を彷彿とさせたのかもしれません。
余談ではありますが、愛知県ではきつねうどんのことを「しのだうどん」と呼ぶそうです。ここでいう「しのだ」とは油揚げのこと。油揚げが乗っている点は同じですが、味付けはさっぱりめな白しょうゆを用いているそうです。
きつねうどん誕生の経緯

実は「きつねうどん」は大阪生まれの料理。大阪に店を構える創業100年以上の老舗うどん店「うさみ亭マツバヤ」が発祥の店とされています。
当初のきつねうどんは、温かいうどんと一緒に油揚げやかまぼこを別皿で提供していたそうです。ところが、いつの間にかお客さんの間で、油揚げをうどんにのせて食べるスタイルが定着。やがてそれをひとつの料理として提供するようになり、現在のようなきつねうどんのスタイルになったようです。
また、最初は「こんこんさん」という名前で親しまれていましたが、後に前述した説から「きつねうどん」という名称に変化しました。
きつねうどんを食べるときに今回の雑学を思い出してみよう

今回の雑学を振り返ってみましょう。
きつねうどんの名前の由来には「油揚げはきつねの好物」とする説や、油揚げの色がきつねに似ているという説があります。大阪の老舗店「うさみ亭マツバヤ」で誕生し、当初は別皿で提供されていた油揚げを客がうどんにのせて食べ始めたことから、現在のスタイルが定着しました。
今回の雑学、きつねうどんを食べるときにでも思い出してみてください。もしかすると、いつもよりもきつねうどんが美味しく感じられるかもしれませんよ。
こんな記事も読まれています
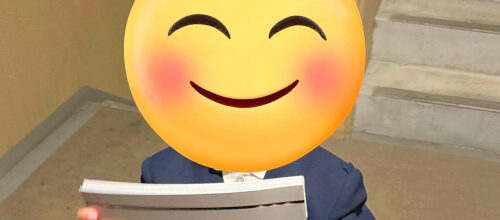 『エレベーター』に詳しすぎる男の子…メーカーの営業マンから貰った”あるもの”を大事そうに抱える姿が483万表示「珍しいマニアw」
『エレベーター』に詳しすぎる男の子…メーカーの営業マンから貰った”あるもの”を大事そうに抱える姿が483万表示「珍しいマニアw」


