信号機で時折鳴り響く「カッコー」「ピヨピヨ音」
街中で耳にする「カッコー」や「ピヨピヨ」という信号機の音。何気なく聞き流している人も多いかもしれませんが、実はこの音には大切な役割があります。
今回は、信号機の発する音の意味について、詳しく解説。最後までお読みいただくと、雑学博士に一歩近づけるかもしれませんよ。
音響式信号機が「カッコー」「ピヨピヨ音」を出す

街を歩いていると、歩行者信号から聞こえる「カッコー」や「ピヨピヨ」という音。実はこの音、視覚障がいのある方が安全に横断歩道を渡るための大切な役割を担っているのです。
音が出る信号機は「音響式信号機」と呼ばれ、信号が青に変わると音を発して歩行者を誘導します。近年では「カッコー」や「ピヨピヨ音」などの擬音式が主流です。
これらの信号機は、盲学校やリハビリセンター、役所などの公共施設が多い地域を中心に設置されており、視覚障がい者の安全な移動を支えています。目が見えない方にとって、なくてはならない大事な信号機なのです。
「カッコー」の意味

音響式信号機から聞こえる「カッコー」と「ピヨピヨ」という音には、それぞれ異なる意味があります。音を使い分けることで、視覚障がいのある方が安全に横断歩道を渡れるよう工夫しているのです。
まず、「カッコー」という音は主道路(交通量の多い道路)に設定されています。この音が鳴ることで、渡る道路の規模を把握しやすくなり、「広い道路だから早めに渡ろう」といった判断がしやすくなるのです。
「ピヨピヨ音」の意味
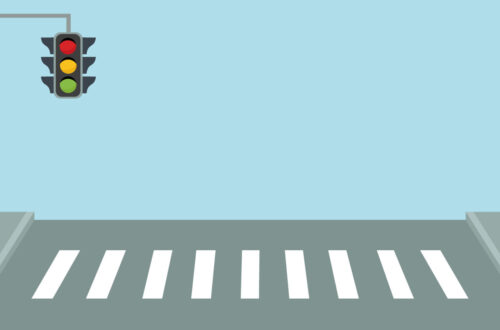
一方「ピヨピヨ音」は従道路(交通量が少ない道路)で使用されます。従道路は主道路よりも道幅が狭く、横断にかかる時間は短め。ですが、車の往来が少なくても運転手から歩行者が見落とされる危険はあります。そのため、音で注意を促し、安全に渡れるよう工夫しているのです。
普段何気なく聞いていたカッコーもしくはピヨピヨ音には、視覚障がい者に道路の種類を伝え、渡る速度などを判断させる材料という意味があったのです。
信号機で音が出ていたら今回の雑学を思い出してみよう!

今回の雑学を振り返ってみましょう。
音響式信号機は、視覚障がい者が安全に横断できるよう音で誘導する仕組み。「カッコー」は交通量の多い主道路で使用され、広い道路を渡る際の目安になります。一方、「ピヨピヨ」は従道路 で使用され、道幅が狭いながらも車に注意を促す役割を担っています。
今回の雑学、信号機で音が出ているときにでも思い出してみてください。
こんな記事も読まれています
 宝くじは連番とバラどっちが当選しやすいの?『宝くじ』にまつわる雑学5選
宝くじは連番とバラどっちが当選しやすいの?『宝くじ』にまつわる雑学5選
 郵便局で『切手』を買おうとしたら…係のお姉さんからの『まさかの提案』が面白可愛いと995万表示「30枚だとおじいさんw」
郵便局で『切手』を買おうとしたら…係のお姉さんからの『まさかの提案』が面白可愛いと995万表示「30枚だとおじいさんw」

