便利なコンビニにまつわる意外と知らない豆知識
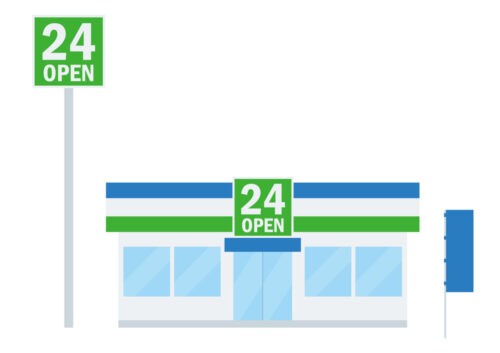
早朝や深夜にも開いていて、幅広いサービスが提供されているコンビニは、今やなくてはならないものへと進化を遂げています。
しかし、そんなコンビニの日本での始まりや経営戦略などは意外と知られていません。そこで今回は、身近で便利な存在であるコンビニの雑学をご紹介します!
コンビニに関する雑学5選

日本初のフランチャイズ制コンビニチェーンは「セブンイレブン」
日本で初めてコンビニエンスストアを作った会社については諸説ありますが、フランチャイズ方式を利用してコンビニをチェーン展開し始めたのは、アメリカ発祥の「セブンイレブン」だとされています。
フランチャイズ方式とは、販売や店内の管理、運営を担うオーナーに企業が看板を貸す形で契約を結び、経営のノウハウを提供する代わりに一定のロイヤリティをもらう形態のこと。
1974年5月に東京・豊洲で第1号店がオープンしてから約50年が経ち、今やコンビニの経営スタイルとしては当たり前のものとなりました。
セブンイレブンで初めて売れた商品はサングラス
セブンイレブンの名前の由来は、営業時間が朝7時から夜11時までだったことに由来します。当時は朝早くから夜遅くまで開いている営業スタイルのお店は珍しく、「いつでもすぐ買える」「なんでも揃っている」という広告にひかれて多くの人が初日から来店しました。
ところが、日本で初めての出店ということもあり、どんなものが売れるのかセブンイレブン側は品揃えに悩んだのだとか。
そんな中で、1番最初の購入客となった男性が買っていったのはまさかのサングラス!アメリカでは売れ筋商品だったため日本でも販売することにしたのですが、気軽に手に取りやすい食べ物などではなく、ファッション用品が先に売れるとは驚きですね。
窓際に本棚があるのは集客力アップと動線の整理のため
取り扱う商品やサービスにそれぞれ特色を出しつつ発展してきたコンビニ各社ですが、窓際に本棚を置く配置については多くの店舗で共通しています。しかも、そこで長時間立ち読みしている人を見かけることも。
実は、本が日に当たって傷むリスクもあるのに窓際に置いているのは、立ち読みする人を外から見えやすくするためです。人気のないお店よりも、にぎわいがあるお店の方がお客さんは安心感を抱き、足を踏み入れやすくなります。
また、比較的長い時間お客さんが滞在するスポットが店内の真ん中や奥にあると、スタッフが品出しなどをしたり、他のお客さんが移動する際の動線が悪くなるため、窓際が選ばれているようです。
お弁当は「ついで買い」を誘う配置になっている
お弁当が奥のスペースにあるのも、店内の商品を売るための戦略です。周囲をよく見ると、お弁当の周りにはお惣菜やサラダ、飲み物やデザートが集まっていませんか?
これは、メインの食べ物を手に取った後、「食べる時には飲み物も一緒に欲しい」「食後に甘いものも食べたい」といった欲求を引き出し、ついでに購入してもらう商品を1つでも増やすためなのです。
近くに同じコンビニチェーンが建つのはわざと!
すでに店舗があるのに、すぐ近くにわざわざ同じコンビニチェーン店を建てるのも、「ドミナント戦略」と呼ばれる経営手法です。
特定の地域に同じ会社のコンビニチェーン店を集めることで、知名度を上げてその地域のお客さんの来店回数を増やし、競合する他社が入り込まないようにしています。
この手法により、セブンイレブンは全国に2万店を超える店舗を構え、コンビニチェーン各社の中で店舗数第1位となりました。ちなみに、第2位は約1万6000店のファミリーマート、第3位は約1万4000店のローソンです。
コンビニを利用する時には雑学を思い出してみよう

今回は、コンビニに関する雑学を5つご紹介しました。何気なくいつも利用しているコンビニの歴史や店内の仕組みを知ると面白いですよね。
今後コンビニを利用する時には、ぜひこれらの豆知識を思い出してみてください。
こんな記事も読まれています
 『非常口マーク』に描かれている人物には名前があった!?あまり知られていない呼び名とは?
『非常口マーク』に描かれている人物には名前があった!?あまり知られていない呼び名とは?
 鮮魚店で巨大な『タカアシガニ』を購入した結果…あまりにも活きが良すぎる様子に846万再生を記録「怖すぎるw」「食べにくいw」
鮮魚店で巨大な『タカアシガニ』を購入した結果…あまりにも活きが良すぎる様子に846万再生を記録「怖すぎるw」「食べにくいw」

