お金をこっそり貯める「へそくり」
「へそくり」と聞くと、こっそり貯めたお金を思い浮かべる人が多いでしょう。家族に内緒で少しずつ貯めるお金として、昔から親しまれている言葉ですが、その語源をご存じですか? 実は、「へそくり」にはいくつか説があると言われています。
今回は、「へそくり」の由来について詳しく解説。最後までお読みいただくと、ちょっぴり物知りになれることでしょう。
そもそも「へそくり」とは…?
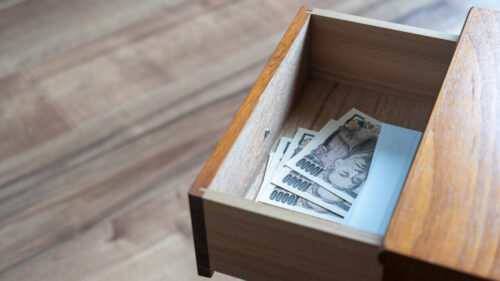
「へそくり」とは、家計とは別に個人でこっそり貯めたお金のこと。配偶者に内緒で蓄えた貯金を指すことが多く、結婚前の貯蓄や夫婦の共有財産とは区別される傾向があります。一般的に、夫婦の生活費からやりくりして捻出したお金を「へそくり」と呼ぶことが多く、時には家庭を支えるための隠し資金として役立つことも。一方で、へそくりの存在が明るみに出ると、少し気まずい雰囲気を生むケースもあるようです。
へそくりの語源として考えられている2つの説

「へそくり」が秘密の貯蓄を意味するようになった背景には、その語源が関係していると考えられています。いくつか説があるものの、有力なものとして「綜麻繰り(へそくり)」説と「臍繰り(へそくり)」説の2つが挙げられます。
まず「綜麻繰り」説。「綜麻(へそ)」とは麻糸を巻きつけた糸束のことで、江戸時代から使われていた言葉です。農村の人々が家計を支えるために内職で糸を紡ぎ、その収入を普段の生活費とは別に管理していたことが、へそくりの由来とされています。
もうひとつは「臍繰り」説。昔の人が「臍(へそ)」の近くにお金を隠していたことに由来します。当時の庶民は財布を持たず、紙に包んだお金を腹巻や帯の中にしまい込んでいました。この習慣が「臍繰り(へそくり)」という言葉につながったとされています。
どちらの説においても、もともと「へそくり」は後ろめたいものではありませんでした。しかし、江戸時代の飢饉や厳しい年貢の取り立てにより、家計を管理する家長のもとでお金の使い道が厳しくなり、隠し財産を持つことが否定的に捉えられるようになったそうです。
さらに、大名に財産を把握されると重い負担を課せられる恐れがあったため、人々はこっそりとお金を貯めるようになり、「へそくり」は密かに蓄えるお金という意味合いへと変化していったのだとか。
へそくりはここぞというときまで大事に貯めておこう!
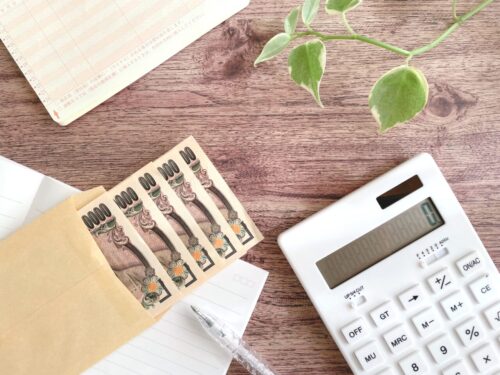
今回の雑学を振り返ってみましょう。へそくりは、家計とは別に個人でこっそり貯めたお金のこと。語源には「綜麻繰り」説と「臍繰り」説の2つがあります。
- 綜麻繰り説:江戸時代、農村で糸巻の内職収入を家計とは別に管理していたことに由来。
- 臍繰り説:庶民が紙に包んだお金を腹巻や帯の中に隠していたことに由来。
もともと後ろめたいものではなかったそうですが、江戸時代の飢饉や厳しい年貢の影響で、財産を隠す意識が強まり、次第に「秘密の貯蓄」という意味へと変化していったとのこと。
今回の記事を参考に、へそくりは大事に貯めていってください。



