そもそも「祈りの日」とは?誰が何のために制定したのか

毎年3月27日は「祈りの日」と呼ばれています。しかし、この日がどのような日なのか知っている人は意外に少ないのではないでしょうか。
実は、「祈りの日」を制定したのは、「全日本宗教用具協同組合」という団体です。2010年(平成22年)に、日本人が古くから大切にしてきた「祈りの文化」を再認識してもらう目的で、この記念日が制定されました。
この日付が3月27日になった理由は、『日本書紀』に記載されている天武天皇の詔に由来しています。天武天皇が686年のこの日に、「国の平和と人々の幸福」を願い、全国に祈りを呼びかけたことが記されています。
つまり「祈りの日」は、単なる語呂合わせや偶然の日付ではなく、歴史上の明確な背景を持った記念日だったのです。
「祈りの日」にまつわるよくある2つの誤解
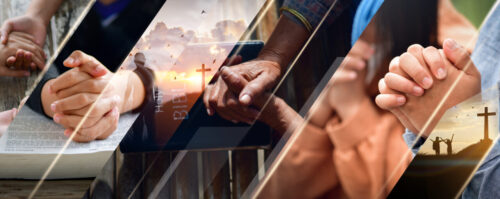
記念日には、よく誤解されているものがあります。「祈りの日」も例外ではありません。ここでは多くの人が誤解しやすいポイントを分かりやすく解説し、その真相に迫ってみましょう。
誤解1 宗教的な記念日ではない?
「祈りの日」と聞いて、多くの人は特定の宗教行事を連想するかもしれません。特に制定した団体の名前が「全日本宗教用具協同組合」なので、「特定の宗教に関係しているのでは?」と思う人もいるでしょう。
しかし、この記念日は仏教や神道、キリスト教など特定の宗教だけに限定された日ではありません。制定の趣旨は、宗教的な行事を行うことではなく、日本人全体が持つ「祈り」という習慣を思い出し、その価値を再認識することです。
例えば、お正月に神社で初詣をしたり、お盆にお墓参りをしたりするように、日本人には日常の一部としての祈りがあります。このように「祈りの日」は、宗教を超えた文化として、誰もが自然な気持ちで向き合える日なのです。
誤解2 「祈りの日」は昔からある伝統行事?
「祈りの日」という名前を聞くと、いかにも古くからの伝統行事のような印象を持つかもしれません。
確かに日本人にとって「祈る」という行為そのものは古代から続いていますが、「祈りの日」という記念日自体が制定されたのは比較的新しいことです。
制定された年は2010年。まだ十数年ほどしか経っていません。つまり、「祈り」という習慣は非常に古い歴史がありますが、この記念日が作られたのはつい最近のことなのです。
古くから続く祈りの習慣に対して、新たに名前と日付を与え、より多くの人に意識してもらうことが狙いだったのでしょう。
日本人はなぜ昔から「祈り」を大切にしてきたのか?

日本では、古くから日常生活のあらゆる場面で「祈り」を行ってきました。その背景にはどのような思いや考え方があったのでしょうか。
単純に「願いを叶えたい」という個人的な目的だけでなく、祈りを通じて日々の生活に安心感や調和をもたらそうという、日本人特有の精神文化があります。
ここからは、この祈りがなぜ日本人の心に浸透しているのかを深掘りし、具体的に見ていきましょう。
祈りが生み出した「日本人の心の余裕」
現代の私たちが忙しい毎日の中で感じにくくなったものの一つが「心の余裕」です。しかし日本人は古来から、「祈る」ことを通じてこの心の余裕を育んできました。
たとえば昔の人々は、農作業を始める前や収穫後に必ず祈りを捧げました。これは単に豊作を願うだけでなく、自分の力だけではどうにもならない自然への敬意を示し、謙虚な気持ちを持つことでもあったのです。
こうした祈りによって「何事も自分の思い通りにはならない」と気持ちを落ち着かせ、困難な状況に直面しても精神的な余裕を失わないように工夫してきました。
つまり日本人にとって祈りは、願いを叶える手段というよりも、心を穏やかに保つための知恵だったのかもしれません。
昔の日本人はどんなことを祈っていたのか
昔の日本人は、日常生活のさまざまな場面で祈りを捧げていました。どのようなことを祈っていたか、その具体例を挙げてみましょう。
まず自然に対する祈りがあります。古代から日本人は山や川、海や田畑といった身近な自然に神々を感じ、その恵みに感謝の気持ちを込めて祈りを捧げてきました。
また健康を祈ることも多くありました。病気やけがが命取りになる時代には、家族が無事に過ごせること自体が大きな願いでした。さらに家庭や子孫繁栄を祈ることも一般的で、自分たちが安心して暮らせる環境を願うことは現代と共通しています。
このように昔の日本人の祈りは、特別な行事や宗教的な枠組みを超えて、日々の暮らしに溶け込んでいました。それは生活に根ざした、ごく自然な営みだったのです。
日本のユニークな「祈り」のトリビア

日本人が日常的に行っている「祈り」の中には、意外な起源や意味が隠れているものがあります。ここでは、特に面白く、つい人に話したくなるようなトリビアを厳選して紹介します。
まず一つ目が「おみくじを引いた後の結び方」です。
おみくじを神社の木や専用の結び場に結ぶのは、実は「神様との縁を結ぶ」という意味があります。意外にも、「悪い結果を置いて帰る」ためだけではなかったのです。
また、「だるまの目入れ」もユニークです。
だるまの目を片方だけ入れて願いをかけ、叶ったらもう片方の目を入れる習慣がありますが、これは「願いが叶うまで片目で見守っている」という意味合いがあります。つまりだるまは、願いを叶えるまでずっとあなたを応援しているのです。
絵馬も面白い背景を持っています。
昔は本物の馬を神社に奉納していましたが、費用がかかるため代わりに「絵に描いた馬」を奉納するようになったことが、絵馬の起源なのです。
このように、何気なくしている行動にも、意外な意味や歴史が込められていることに気づくと、日本の祈り文化がもっと楽しくなりますよね。
「祈りの日」の由来を雑談ネタにしよう

「祈りの日」について色々知ると、人に話したくなりませんか?雑談として話題にするなら、少し意外で簡単なトピックが喜ばれます。
たとえば、『日本書紀』と聞くと「歴史の授業で出てきた難しい本」というイメージがありますが、その中に「祈りの日」の起源となった天武天皇の詔が載っているというのはちょっと意外な話です。友達や家族に話すとき、「『日本書紀』って実は記念日のルーツにもなっているらしいよ」と切り出してみるのもいいでしょう。
また、「祈りの日」を制定した団体が「宗教用具協同組合」というのも面白いポイントです。「意外な団体が記念日を作っているんだよ」と軽く紹介するだけでも、相手が興味を持つきっかけになるはずです。
このような小さな雑学から、会話が広がることもあります。ぜひ気軽に話題にしてみてくださいね。



