壁にある差し込み口がコンセント

電子機器の充電をする時や、家電を使う時には必須となるのがコンセント。
言葉があいまいになりがちですが、2つの突起がある電源コードの先端はプラグであり、コンセントとは壁にある差し込み口のことを意味します。
今回は、室内に当たり前のようにあるコンセントの意外と知らない雑学をご紹介しましょう。
コンセントにまつわる雑学4選

コンセントの差し込み口の長さは左右で違う
電化製品に電気を流したい場合、コンセントには電源プラグを挿して使用します。その差し込み口をよく見ると、コンセントに開いている2つの細長い穴は左が9mm、右が7mmと、左右で大きさが異なっています。
実は、コンセントの穴は右の穴から電気が入ってくることで各製品が使えるようになっており、反対に左側の穴は電気をコンセントに返す役割が備わっているのです。
もしも高い電圧の電気が流れるようなことがあれば、左の穴から地面に電気を逃がすことで感電を防止できるという安全装置になっています。
コンセントに挿すプラグの向きにも注目
コンセントの左右の穴の大きさが違っているにも関わらず、プラグの先端についている2本の刃のサイズはほとんどが同じ大きさです。
一般的には、コンセントの穴の大きさに合うのがどちらの刃なのかを気にせず挿し込めるよう電化製品側の配線に工夫が施されているため、プラグの向きを気にする必要はありません。
しかし、音質が重要になるAV機器に関しては話が異なります。音楽などを再生した時に発生してしまう雑音(電気的なノイズ)は、コンセントの左の穴から逃がす仕組みになっているため、プラグの刃を挿し込む向きが大切になってくるのです。
左の穴に挿し込む刃がどちらなのか見分けられるよう、プラグがつながるコードには白線を引いてマークしてあることも多いため、より良い音を楽しむためにも使用時にはぜひ注目してみてください。
プラグに穴が開いているのはコンセントのため
プラグの細長い先端には丸い穴が開いていますが、これはコンセントの内部にある突起にはまって抜けにくくなるようにと作られているものです。
プラグが半端に抜けかけた状態だと、挿し込んでいるところにほこりが溜まりやすくなり、そのまま電気を供給し続けるうちに最悪のケースでは発火する「トラッキング火災」が起こる危険もあります。
台所や洗面所など、湿気の多い場ではほこりつきのプラグは放電と発熱を繰り返しやすく、ショートするリスクが増すため、プラグがコンセントにきちんとはまっているかや、変形がないかどうかなどを日頃からよく確認しましょう。
また、定期的に汚れを掃除して取り除いたり、使っていない電化製品があれば、コンセントからプラグを抜いておくのもおすすめです。
コンセントは和製英語
コンセントはカタカナで表記されるため、英語からきた言葉だと思いがちです。しかし実は、コンセントという言葉は和製英語で、海外の人にそのまま伝えても通じません。
コンセントを英語にすると、「outlet(アウトレット)」や「socket(ソケット)」と言います。主に「outlet」はアメリカ英語、「socket」はイギリス英語で使われることが多いので、どこの国の人と話すかに応じて変化させると良いでしょう。
ちなみに、電源ケーブルの先についているプラグの部分は、英語でも同じく「plug(プラグ)」と言います。
コンセントは正しく安全に使おう
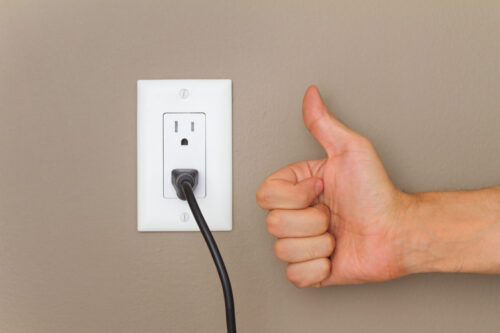
いつも使っているはずなのに、コンセントの仕組みについては知らないことが多いもの。穴の大きさが違うのは、電気の流れにまつわる役割の違いがあるからです。
基本的にはプラグの向きなどは気にせず挿し込めますが、コンセントの左右の穴の違いが各製品を使う時の質を変化させることもあります。
正しい使用方法を確認しながら、安全にコンセントを使っていきましょう。
こんな記事も読まれています
 『水族館』で夫が撮った写真を見返してみたら…ママに起きた衝撃的な異変に2521万表示の大反響「迫力凄すぎるw」「爆笑した」
『水族館』で夫が撮った写真を見返してみたら…ママに起きた衝撃的な異変に2521万表示の大反響「迫力凄すぎるw」「爆笑した」


