『火鉢』と『七輪』
寒い季節になると、昔ながらの「火鉢」や「七輪」を使った温かい暮らしに憧れる方も多いのではないでしょうか。どちらも炭を使う道具ですが、見た目や用途には意外な違いがあります。「調理に使うならどっちが便利?」と悩んでいる方にとっては、その使い勝手の差は気になるところ。
今回は、火鉢と七輪の違いをわかりやすく解説。最後までお読みいただくと、ちょっぴり物知りになれることでしょう。
火鉢とは

火鉢は、かつて日本の家庭で広く使われていた暖房器具。昭和30年代ごろまでは生活に欠かせない存在でした。現在では珍しいものですが、昔はどの家庭にもあるごく一般的な道具でした。
その起源は平安時代にさかのぼり、中国から伝わったものとされています。当初は貴族が主に用いる暖房具で、手をかざしたり、空間を暖めたりするために使われていたと言われています。時代が進むと、江戸時代には持ち運びができる囲炉裏のような役割として火鉢が発展。庶民の間にも広まりました。
庶民の家庭では陶器製の火鉢が一般的でしたが、武士や商人、あるいは人が多く集まる豪農の家などでは、木製の火鉢が使われていたそうです。
七輪とは

七輪は、炭火を使って調理する昔ながらのコンロみたいなもの。主に焼き物や煮炊きに活用されてきました。江戸時代から庶民の暮らしに根づいており、今でもキャンプや家庭用の炭火調理器具として人気があります。
本体は断熱性に優れた珪藻土で作られており、外側が熱くなりにくいため安全性も高め。また、軽くて小型なので持ち運びしやすく、屋外での使用にも向いています。
七輪にはいくつかのタイプがあり、自然の珪藻土をそのまま削り出して作る「切り出し七輪」や、練った珪藻土を型に入れて成形する「練り七輪」などがあります。
名前の由来については諸説ありますが、炭の価格が「七厘」だったことや、底に空気穴が7つあったことが関係しているとも言われています。
『火鉢』と『七輪』の違い

「七輪」と「火鉢」は、どちらも炭を使いますが、使い道などに大きな違いがあります。
七輪は主に屋外での調理に使われる道具。珪藻土という断熱性の高い土で作られています。魚を焼いたり、焼き肉をしたりと、油がはねるような料理にも対応できるのが特徴です。火に直接網をのせて焼けるため、アウトドアや庭先でのバーベキューにもぴったり。
一方、火鉢は室内用の暖房器具として使われてきたもの。陶器や木でできており、内部には灰が入っています。炭を灰の中に埋めてじんわりと熱を保つ構造のため、鉄瓶でお湯を沸かしたり、餅を焼いたりするのに適しています。ただし、直接肉などを焼くのには向いていません。
七輪は調理向き、火鉢は暖をとるための道具と覚えておくと、それぞれの特徴がよく理解できるでしょう。今回の雑学、面白かったらぜひ周りの人にも教えてあげてみてください。
こんな記事も読まれています
 レッドカーペットの意味と由来とは?結婚式や式典で敷かれる理由を徹底解説!
レッドカーペットの意味と由来とは?結婚式や式典で敷かれる理由を徹底解説!
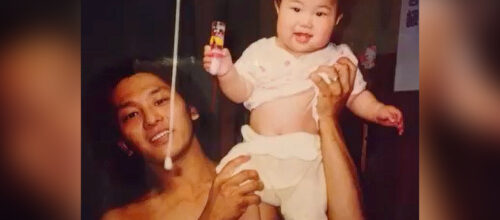 長女の誕生と共に25年間『筋トレ』を続けた男性が…現在の姿が若々しすぎると34万再生「47歳には見えない」「かっこいい!」
長女の誕生と共に25年間『筋トレ』を続けた男性が…現在の姿が若々しすぎると34万再生「47歳には見えない」「かっこいい!」

