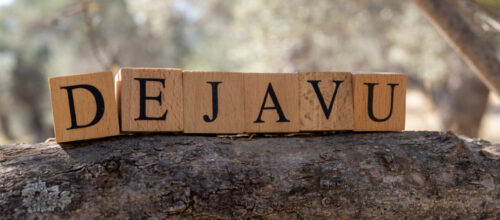「ホッキョクグマ」と「シロクマ」
寒い地域に生息する真っ白なクマといえば「ホッキョクグマ」や「シロクマ」という名前を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、「ホッキョクグマ」と「シロクマ」は別の動物なのか? それとも同じものを指すのか?気になりませんか?
今回は、ホッキョクグマとシロクマの違いについて分かりやすく解説。クマについて詳しくなれるので、ぜひ最後まで読んでみてください!
まずは「ホッキョクグマ」について解説

ホッキョクグマはクマ科に属する動物で、地上最大級の肉食動物です。主に北極圏に生息しています。冬の間は氷の上で生活し、アザラシを中心に狩りを行います。一方、夏になると氷が溶けてしまうため、陸に移動してほとんど食べずに過ごします。
もともとはヒグマと共通の祖先を持ち、進化の過程で寒冷地に適応しました。学名の「Ursus maritimus」は「海のクマ」という意味で、その名の通り、泳ぎが得意で海中に潜ることもできるのが特徴です。
続いて「シロクマ」について解説

ヒグマやツキノワグマなどのクマは、遺伝子の突然変異によってまれに白い体毛を持つ個体が生まれることがあります。これらは「アルビノ」と呼ばれます。
かつて動物園では通常の黒いクマと区別するために「シロクマ」として展示されていました。つまり、本来「シロクマ」とはホッキョクグマとは異なり、アルビノのクマを指す言葉だったのです。
「ホッキョクグマ」と「シロクマ」の違い

ホッキョクグマは白く見えますが、実は肌が黒く、体毛自体は透明です。透明な毛が光を反射することで、白く見える仕組みになっています。
かつて動物園では、遺伝子の突然変異で体毛が白くなったアルビノのクマと、北極圏に生息するホッキョクグマを区別する必要がありました。こうした理由から、アルビノの白いクマを「シロクマ」、北極圏に生息しているクマを「ホッキョクグマ」と呼称するようになったそうです。
とはいえ現在では、白いクマ全般を「シロクマ」と呼ぶことが一般的。厳密に区別されることは少なくなっています。
ホッキョクグマ、シロクマを見かけたら今回の雑学を思い出してみよう

今回の雑学を振り返ってみましょう。
ホッキョクグマは北極圏にいるクマ。冬は氷上でアザラシを狩り、夏はほとんど食べずに過ごします。泳ぎが得意で、学名は「海のクマ」を意味します。一方、シロクマはアルビノの白いクマを指す言葉。現在では白いクマ全般をシロクマと呼ぶことが一般的で、厳密な区別はあまりされていません。
今回の雑学、動物園などでホッキョクグマ、シロクマを見かけたら思い出してみてください。