日常でよく使う「まじ」
「まじで!?」「それ、まじ?」といった具合に日常会話でよく使われる「まじ」。実は、江戸時代から使われていたこと、みなさんご存じでしょうか? さらに、他にも現代の若者言葉と思われがちな言葉が、昔から存在していたのです。
今回は、「まじ」の歴史について詳しく解説!最後までお読みいただくと、言葉博士に一歩近づけることでしょう。
そもそも「まじ」とはどういう意味?
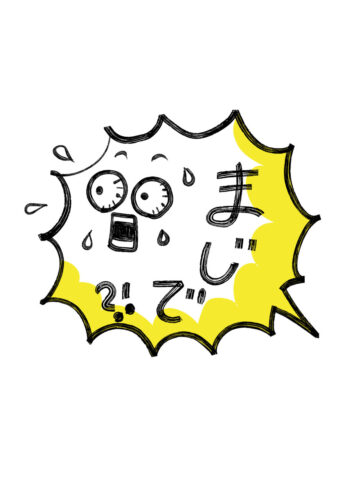
まずは、現代における「まじ」がどういった意味なのかから解説していきましょう。「まじ」という言葉は、「まじめ」を省略したもの。「本気」や「真剣」、「本当」を意味し、1980年代から若者の間で広まりました。
「まじ」は昔からあった

そんな「まじ」ですが、実は昔から既に存在していました。元々「まじ」という言葉は、江戸時代の芸人たちが使っていた楽屋言葉(業界用語)のひとつ。
当時も「真面目」の略語とされており、歌舞伎作品『当穐八幡祭(できあきはちまんまつり)』にも「ほんに男猫も抱いて見ぬ、『まじ』な心を知りながら」…というセリフがあったようです。日常で当たり前のように使っていましたが、意外と古い言葉だったのですね。
昔から使われていた若者言葉は他にもある!

昔に誕生していた若者言葉は「まじ」の他にも存在します。たとえば、下記のような言葉が挙げられます。
- ビビる
- キモイ
- ムカつく
- モテる
まず、「ビビる」は、平安時代に戦の最中に鎧がぶつかり合う音「ビンビン」に由来し、武士たちがその音を「びびる音」と呼んだとも言われています。また、江戸時代には、舞台前で緊張している芸人たちを指して「びびる」と表現したともされています。
続いて「きもい」も、現代では「気持ち悪い」の略語として広く使われていますが、江戸時代には「窮屈で不快」という意味で使われていました。
次は「ムカつく」。平安時代後期から使われており、元々は体調が悪いときに「胸やけ」や「吐き気」を指していました。その後、「腹が立つ」という意味でも使われるようになりました。
もうひとつ、「モテる」も江戸時代には誕生していました。元々は「持てる」が語源。最初は「持ち得る」という意味から派生し、やがて「支えられる」や「もてはやされる」という意味になりました。
今回の雑学、面白かったら周りの人にも教えてあげよう!

今回の雑学を振り返ってみましょう。
「まじ」は江戸時代から存在しており、当時は芸人たちの楽屋言葉として使われていました。元々「真面目」の略で、江戸後期の歌舞伎作品にも登場しています。その他にも、ビビる・キモイ・ムカつく・モテるなども、昔から使われていました。まじ驚きですよね。
今回の雑学、面白かったらぜひ周りの人にも教えてみてください。実は若者言葉の一部が昔からあると知ったら、きっと驚くことでしょう。



