江戸時代の寿司が大きい理由は意外とシンプルだった

「昔の寿司って、そんなに大きかったの?」と思った方、けっこういるのではないでしょうか。
現代の寿司は一口サイズで、上品にパクッと食べられるのが当たり前。でも、江戸時代の寿司はその常識をくつがえすようなサイズ感でした。実は、ネタもシャリも今よりずっと大きくて、まるで小さなおにぎりのような迫力だったんです。
では、なぜそんな“でかい寿司”が生まれたのか――。
それには、当時の屋台文化や保存技術、使っていたお米の性質など、意外とシンプルだけど納得できる理由がありました。この記事では、江戸時代の寿司がなぜ大きかったのか、その背景をわかりやすくご紹介します。昔の寿司の姿を知ると、今の寿司がちょっと違って見えるかもしれません。
江戸の寿司は現代の3倍サイズ

現代の握り寿司は、一貫あたりだいたい20~30g程度の大きさです。手にとって一口でパクッと食べられるサイズ感ですよね。
ところが、江戸時代の寿司のサイズはなんと、現代の約3倍の大きさで、一貫あたり約78gもあったのです。イメージとしては、小さなおにぎりや軽食用のパンほどのボリューム感。これを一口で食べるのはかなり難しそうですよね。
また、シャリの量も今の約3倍で、ぎゅっと握られていました。当時の寿司を再現したイラストや写真を見ると、その大きさと迫力にびっくりする人が多いでしょう。
江戸の寿司は「でかい」が普通。このサイズ感こそが、江戸時代の握り寿司の特徴でした。
なぜ江戸時代の寿司は大きくなった?

江戸時代の寿司が大きかった背景には、大きく分けて3つの理由があります。当時の人々の生活スタイルや社会環境が関わっているので、それぞれを簡単にストーリー形式でご紹介しましょう。
屋台で働く江戸っ子は腹ペコだった
江戸時代の寿司が大きかった最も大きな理由の一つが、寿司を食べる主な対象が「屋台で食事をとる労働者たち」だったことです。当時の江戸は急速に人口が増え、商業活動も活発になっていました。
江戸っ子は朝から晩まで忙しく働き、しっかりとした食事をとる暇がありませんでした。そんな彼らにとって、短時間で手軽に食べられて満腹感を得られる食事が求められていたのです。
寿司屋台は、そんな忙しい江戸っ子たちに人気のスポットでした。注文すれば、待たずにすぐ出てくる大きな寿司。労働者にとっては、短時間でエネルギーを補給できるありがたい存在だったのです。
例えば、当時の記録には「寿司二つでお腹いっぱいになる」という記述もあります。現代人なら5~6貫は余裕で食べられるところですが、江戸の大きい寿司なら2貫でも満足できるほどでした。
江戸時代の寿司屋台の風景を想像すると、忙しく働く人々の暮らしが目に浮かんできますね。
冷蔵庫がないからネタを工夫した
江戸時代にはもちろん冷蔵庫など存在しません。そのため、生の魚をそのままネタにして寿司にすることは、ほとんどありませんでした。魚介類は腐りやすく、生でそのまま提供すると食中毒の危険もあったのです。
そこで、当時の寿司職人たちはさまざまな工夫を凝らしました。特に多用されたのが「酢締め」です。魚を酢で締めると保存性が高まる上に、酢の風味が加わって美味しく食べられるからです。
また、醤油やタレに魚を漬け込む「漬け」も人気でした。昆布で包んでうま味を加える「昆布締め」、タコやエビなどを茹でたり煮たりして火を通す加工方法もよく行われました。
こうした加工法ではネタが縮んだり崩れたりしないよう、大きめに切り分けることが多くなります。そのため、自然と寿司ネタも大きくなり、結果的に寿司全体が大きくなったわけです。
現代では「新鮮=美味しい」と考えがちですが、江戸前寿司のネタは「ひと手間かけた旨さ」が特徴でした。酢締めや漬けなどの加工をすることで、寿司ネタはより味わい深くなり、江戸の人々に愛される味となったのです。
米の特性でシャリも巨大化した
寿司といえば、ネタと並んで重要なのがシャリですよね。江戸時代のシャリは、現代の寿司とは大きな違いがありました。その理由は、当時の米の性質にありました。
江戸時代に使われていたお米は、粒がやや大きく粘り気が少なかったと言われています。そのため、現代のように小さくてまとまりの良いシャリを作るのは難しく、大きめに握ることで崩れないように工夫していました。
また、当時のシャリには「赤酢」と呼ばれる酒粕から作られたお酢が使われていました。この赤酢は、現在の一般的なお酢より色が濃く、シャリにほんのり赤みを帯びさせます。見た目にも特徴的で、独特のまろやかな味わいがあったようです。
この赤酢を使ったシャリを大きく握ることで、酢の香りとお米の食感をしっかり楽しめるのが、江戸時代の握り寿司の魅力でした。現代の小さくて軽いシャリとは異なり、まるで小さなおにぎりのような食べ応えがあったのです。
昔のお寿司は、シャリひとつをとっても、時代の違いを感じられる工夫が詰まっていたんですね。
大きい寿司が江戸中で人気になった理由
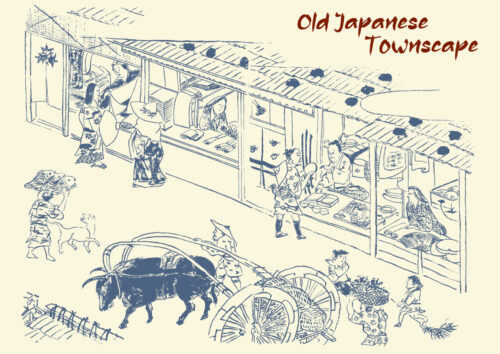
こうした大きな寿司は、単にサイズが大きいだけでなく、当時の江戸の暮らしや食文化にもぴったりと合ったものでした。では、具体的にどうして江戸の人々の間で人気が広まったのでしょうか。ちょっとその様子をのぞいてみましょう。
寿司屋台が庶民にウケた
江戸の街には屋台が並び、手軽で安い食事が楽しめる文化がありました。特に寿司屋台は、その中でも人気が高く、多くの江戸庶民が集まりました。
人気の理由は「安くて、早くて、腹いっぱい食べられる」こと。忙しく働く職人や商人、庶民たちにとって、手軽で美味しくて腹持ちの良い食事は理想的でした。
例えば、当時の職人たちは仕事の合間にさっと寿司屋台に立ち寄り、大きな寿司を一、二貫食べてお腹を満たしていたようです。価格も手頃で、誰でも気軽に楽しめることから、屋台寿司は次第に江戸の庶民の生活に欠かせない存在になりました。
江戸時代の寿司屋台は、今で言うファストフード店のような存在だったと言えるでしょう。こうして手軽さと満足感を兼ね備えた寿司が、江戸の町に広まっていったのです。
大きなネタが江戸っ子の評判に
寿司が江戸で広まったもう一つの理由は、大きなネタが評判を呼んだことでした。
当時はネタの種類も少なく、生魚は扱いにくかったため、ひとつひとつのネタを大きく加工して工夫を凝らすことで特徴を出していました。例えば、大きく酢で締めたコハダやマグロの漬けなどは、見た目にもインパクトがあり、美味しさも評判でした。
また、江戸っ子たちは「見栄え」にも敏感でした。ネタが大きい寿司は見た目にも豪華で、江戸っ子の気質に合っていたのです。そうした大きなネタを使った寿司が口コミで広まり、人気がさらに高まったというわけです。
現代でも東京には「ネタが大きい寿司屋」がありますが、そのルーツはまさに江戸時代にあると言えるでしょう。
江戸時代の寿司を現代で再現してみたら?

ここまで江戸時代のお寿司について話をしてきましたが、「実際に食べてみたらどんな感じなんだろう?」と気になった方もいるのではないでしょうか。そんな疑問を持つ人も多く、実際に当時の寿司を再現する試みが各地で行われています。
ある寿司屋では、江戸時代の文献を参考に、当時のお寿司を忠実に再現しました。その寿司のシャリの量は、なんと現代の約3.5倍!ネタも酢締めや漬けなどの加工をしており、全体的にかなりボリュームがある見た目でした。
再現寿司を食べた現代の人の感想は、まず「食べにくい!」という意見が多かったようです。なにせ一口では食べられない大きさですから、かぶりつくのが精一杯。箸や手で半分に分けて食べる人もいたほどです。
ただ、その一方で「満足感は抜群」「酢締めのネタが意外に美味しくて、現代寿司とは違う深い味わいがある」と評価する人も多くいました。
江戸時代の寿司は「ただ大きいだけ」ではなく、味の深みや満足感も現代とは違った魅力を持っていたようですね。
昔の寿司の話誰かに話してみませんか?
ここまで江戸時代の寿司が現代よりも大きかった理由を見てきました。大きさの理由は、
- 屋台で手軽に満腹感を得られる必要があったこと
- 冷蔵技術がなくネタを加工していたこと
- 当時のお米の特徴からシャリが大きくなったこと
という社会背景や食文化に由来していましたね。
この話を知っていると、普段食べる寿司がちょっと違った視点で楽しめるかもしれません。ぜひ、家族や友達との食事の席で「実は昔の寿司はこんなに大きかったんだよ」と話してみてください。きっと盛り上がること間違いなしです。
寿司という身近な食べ物にも、こんな奥深い歴史や背景が隠されているなんて面白いですよね。江戸時代のお寿司が持つユニークなエピソードを、ぜひ誰かに教えてあげましょう。
こんな記事も読まれています
 オヤツを食べようとする『赤ちゃん』…なかなか食べられない姿が面白すぎると34万再生「不思議そうにしてて可愛いw」「マジシャンかな?」
オヤツを食べようとする『赤ちゃん』…なかなか食べられない姿が面白すぎると34万再生「不思議そうにしてて可愛いw」「マジシャンかな?」


