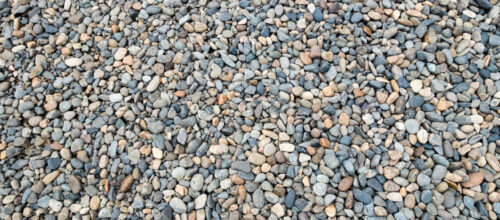『抹茶』と『緑茶』

私たちの生活に身近なお茶。中でも「抹茶」と「緑茶」は、どちらも緑色をしていて似た印象を受けますが、実はいくつか違いがあります。
今回は抹茶と緑茶に関する面白い雑学をお届け。最後までお読みいただくと、抹茶や緑茶が飲みたくなるかもしれませんよ。
そもそも抹茶とは

抹茶は、緑茶の一種で、茶葉をまるごと粉にしていただくお茶です。原料となるのは「碾茶(てんちゃ)」という茶葉。茶摘みの前に日光を遮って育てた茶葉を蒸したあと、揉まずに乾燥させたものです。この碾茶を石臼などで丁寧に挽いて粉末状にしたものが抹茶です。
緑茶といっても種類はさまざま。よく知られる「煎茶」などは茶葉を急須で淹れて飲みますが、抹茶はお湯に溶かしてそのまま飲むのが特徴です。まろやかな甘みとうま味が強く、渋みが少ないのも魅力のひとつ。茶道のお点前で使われるほか、最近ではスイーツやドリンクなどにも広く活用されています。
それでは緑茶とは

緑茶とは、茶葉を発酵させずに仕上げたお茶のこと。日本では最もポピュラーなお茶の種類です。お茶は製造過程での「発酵」の程度によって分類され、緑茶は発酵させない「不発酵茶」にあたります。
- 煎茶
- 玉露
- 抹茶
- 番茶
- ほうじ茶
緑茶とひと口にいっても、いくつかの種類があります。たとえば、最も一般的な「煎茶」は、蒸した茶葉を揉んで乾燥させて作られます。「玉露」は育て方に工夫があり、収穫前に日光を遮ることでうま味が強くなります。同様に日陰で育てた茶葉を粉末にしたものが「抹茶」です。「番茶」は煎茶よりも大きめの葉を使い、香ばしく焙煎した「ほうじ茶」や、玄米を混ぜた「玄米茶」なども、緑茶に分類されます。
緑茶は国内で生産される茶葉の大部分を占めていると言われており、日本人にとって馴染み深いお茶といえます。
抹茶や緑茶を嗜むときに今回の雑学を思い出してみよう

今回の雑学を振り返ってみましょう。
抹茶は緑茶の一種で、「碾茶(てんちゃ)」と呼ばれる茶葉を粉末状にしたもの。碾茶は、収穫前に日光を遮って育てられた茶葉を蒸し、揉まずに乾燥させて作られます。抹茶はお湯に溶かしてそのまま飲むため、茶葉の栄養をまるごと摂れるのが特徴です。甘みとうま味が強く、茶道をはじめ、スイーツや飲料にも広く使われています。
一方、緑茶とは発酵させずに作られる「不発酵茶」のことで、日本で最も親しまれているお茶の分類です。煎茶や玉露、番茶、ほうじ茶などがあり、それぞれ製法や風味が異なります。たとえば、煎茶は蒸した茶葉を揉んで乾燥させたもので、急須で淹れて飲むのが一般的。玉露や抹茶のように日陰で育てた茶葉は、よりうま味が強くなる傾向があります。
このように、抹茶は緑茶の一種でありながら、製法や飲み方、使われ方において独自の特徴を持っています。
今回の雑学、抹茶や緑茶を嗜むときにでも思い出してみてください。もしかすると、いつもより抹茶・緑茶が美味しく感じるかもしれませんよ。