知れば知るほど面白い『お年玉』の歴史

「お年玉、今年はいくらもらえるかな?」
子どもの頃、誰もが心躍らせた瞬間ですよね。真新しいお札が入ったポチ袋を手にした時の、あの独特なワクワク感は今でも覚えているという方も多いのではないでしょうか。
でも、実は昔のお年玉は、今とはまったく違う姿をしていました。驚くことに、お金ではなく「餅」だったのです。これには深い意味が込められていて、実は私たちの先祖の願いや知恵が詰まっているんです。
お年玉はどうして「餅」から始まったのか

昔の人々は、お正月になると「歳神様(※1)」という神様をお迎えしていました。この神様は、その年の幸せや豊かさをもたらしてくれる大切な存在。各家庭では、歳神様を迎えるために丸い鏡餅を用意していたのです。
このお供えした鏡餅には、実はある重要な役割がありました。歳神様が宿る「依り代(※2)」としての役割です。古い文献には「歳神様は鏡餅に魂を込めて帰られる」という記述が残っているほど、大切にされていたようです。
そして松の内が終わる頃、この神聖な鏡餅は家族に分け与えられました。これこそが「御歳魂(おとしだま)」と呼ばれ、現代のお年玉の原型となったのです。単なる食べ物ではなく、その年を元気に過ごすための「生命力」として、大切に分け合われていたんですね。
※1:歳神様:五穀豊穣をもたらすとされる年の神様。新年に各家庭を訪れ、その年の幸せを授けてくれると信じられていました。今でいえば、新年の幸運を運んでくれる特別な存在というイメージです。
※2:依り代:神様が宿る場所や物のこと。神様の力が宿ると考えられた特別な存在で、現代で例えるなら、スマートフォンの充電器のような役割を果たすものだと考えるとわかりやすいかもしれません。
意外と知らない「御歳魂」の深い意味
面白いことに、「トシ」という言葉には「稲や稲の実り」という意味もありました。つまり、お年玉の起源には、その年の豊作を願う農耕文化の知恵も隠されていたというわけです。家族で分け合う餅には、こんなにも深い願いが込められていたんですね。
当時の様子を想像してみてください。家族が集まり、一年の無事を願いながら餅を分け合う。そこには、今のようなお金のやり取りとは違う、温かな家族の絆を感じますよね。
餅からお金へ、変化の理由に驚き

「でも、なんでお金を渡すようになったの?」
実は、お年玉が現金になっていく過程には、とても興味深い歴史があります。江戸時代、商家では使用人への感謝を込めて「心づけ」としてお金を渡すようになりました。これが、現金でのお年玉の始まりと言われています。
面白いことに、この時代のお年玉は、その人の職業によって形が異なっていました。武士は太刀を、町人は扇子を、医者は丸薬を贈るなど、贈り主の個性が光る習慣だったのです。
ある古い記録には「商家の主人から新年の心づけをもらった使用人が、一年を通じて誠実に働いた」という記述も。お年玉には、単なる贈り物以上の、人と人とのつながりを深める大切な役割があったようです。
高度経済成長がもたらした大きな変化
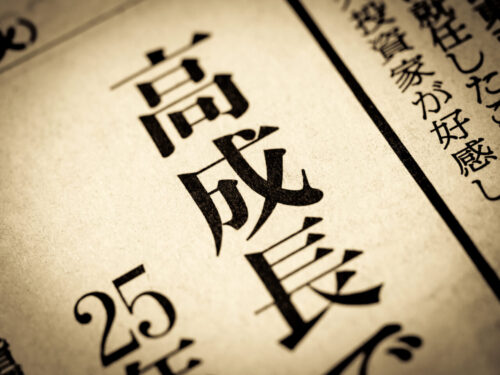
現在のような形、つまり「お金を包んで渡す」というスタイルが定着したのは、実は昭和30年代以降のことです。高度経済成長期に入り、日本の生活様式が大きく変化したのがきっかけでした。
80代のおばあちゃんは、当時をこう振り返ります。
「私が子どもの頃は、近所のおじいちゃんから手作りの餅をもらうのが楽しみでした。でも、団地に引っ越してからは、お餅を作る家がどんどん減っていって…。その代わり、お年玉袋にお金を入れてくれるようになったんです。時代の流れを感じましたね。」
世界でも珍しい日本のお年玉文化
お金を贈り物とすることに抵抗がある国も多い中で、日本では「心を込めて包む」という独特の作法と共に、このお年玉文化が大切に受け継がれてきました。形は変われど、相手を想う気持ちは昔も今も変わっていないのです。
実際、お年玉を包む際の丁寧な所作や、ポチ袋のデザインの美しさなど、日本ならではの繊細な心遣いが息づいています。これは、贈る側も受け取る側も、お金以上の価値を感じ取れる素晴らしい文化と言えるのではないでしょうか。
意外と奥深い!現代のお年玉文化のカタチ

お年玉は時代と共に形を変えながらも、日本の大切な文化として定着してきました。最近では、お年玉を通じて子どもにお金の大切さを教える良い機会という声も。
でも、ちょっと待ってください。実は私たちが当たり前だと思っているお年玉には、知っているようで知らない豆知識がたくさんあるんです。
お年玉の基本、ポチ袋の秘密
「ポチ袋」という名前の由来を知っていますか?実は関西の方言から生まれた言葉なんです。「ぽちっと」という言葉には「少しだけ」という意味があり、「これっぽっち(これだけ)」という謙虚な気持ちを表現していたんです。
また、このポチ袋には、お金をそのまま渡すことを避けたいという日本人特有の心遣いが込められています。一説によると、江戸時代、商人たちが商売以外でお金を直接手渡しすることを良しとせず、紙に包んで渡すようになったのが始まりだとか。
知って得する!現代のお年玉事情
最近では、お年玉の渡し方も多様化しています。現金だけでなく、図書カードやギフトカードを選ぶ人も増えてきました。特に、目上の方のお子さんにお年玉を渡す際は、現金ではなくギフトカードを選ぶ方が無難とされています。
ある30代の会社員はこう語ります。
「上司の子どもにお年玉を渡すとき、どうしようか迷いました。先輩に相談したら、『図書カードがいいよ』とアドバイスをもらって。確かにその方が気持ちも伝わりやすいし、教育的な価値もありますよね」
アジアに広がるお年玉文化の輪

実は、お年玉のような習慣は日本だけのものではありません。アジアの近隣諸国にも、似たような文化が存在するんです。
中国では「圧歳銭(あつさいせん)」(※3)と呼ばれる習慣があります。面白いことに、これには魔除けの意味が込められています。「歳」と「祟(たた)り」が同じ発音であることから、お金を渡すことで子どもたちを邪気から守るという考えがあったそうです。
一方、韓国では比較的新しい文化として定着したようです。ただし、日本のようにポチ袋は使わず、現金をそのまま渡すのが一般的。これは、親近感の表れとも言えるかもしれません。
※3:圧歳銭:中国の旧正月に子どもたちに渡される、縁起物としてのお金。赤い封筒に入れて渡すのが特徴です。日本のポチ袋が和紙で作られることが多いのに対し、中国の紅包(こうほう)は鮮やかな赤色が特徴的です。
思わず誰かに教えたくなる!お年玉にまつわる面白発見

お年玉の文化は、時代とともに少しずつ形を変えながらも、私たちの生活に深く根付いています。でも、この文化には実はまだまだ知られていない面白い一面があるんです。
お年玉と言えばピン札?実はそうでもない
「お年玉はピン札で渡さなきゃ」という声をよく聞きますが、実はこれ、それほど厳密な決まりではないんです。むしろ、新札にこだわりすぎて銀行に並ぶ必要もありません。
昭和初期には、お年玉用の新札を用意することなど、ほとんどの家庭ではできなかったそうです。大切なのは「きれいなお札」であること。極端に傷んでいなければ問題ないというのが、今では一般的な考え方になっています。
意外と知らない!ポチ袋選びの楽しみ方
最近のポチ袋は、デザインの種類が豊富で選ぶ楽しみも増えています。キャラクターものから和風モダンまで、センスの見せどころとして注目する人も。特に面白いのが、その年の干支をモチーフにしたデザイン。毎年集めている人もいるそうです。こんな楽しみ方もあるんですね。
お年玉文化から見える日本人の心
お年玉の歴史を紐解いていくと、そこには日本人特有の気遣いや考え方が隠されています。お金を「包む」という行為一つとっても、相手を思いやる気持ちが形になっているんです。
あるお年寄りは「戦後の貧しい時代でも、近所のおばあちゃんが小銭を包んでくれた。その時の温かい気持ちは今でも忘れられない」と語ってくれました。金額の大小ではなく、その真心が子どもの心に深く刻まれるんですね。
素敵な思い出は、次の世代へ
お年玉の文化には、世代を超えて受け継がれる価値があります。子どもたちにとっては、お金の大切さを学ぶ機会にもなりますし、何より「大切にされている」という実感を得られる瞬間でもあるのです。
知っているようで知らなかったお年玉の歴史。この話を聞いた誰かが「へえ、そうだったんだ!」と驚くかもしれません。そんな会話が、この素敵な文化を未来へとつないでいくのかもしれませんね。
こんな記事も読まれています
 『空手教室』に入門したばかりの男の子…女の子相手に無抵抗なワケを聞いた結果、”まさかの返答”に128万再生の反響「惚れた」
『空手教室』に入門したばかりの男の子…女の子相手に無抵抗なワケを聞いた結果、”まさかの返答”に128万再生の反響「惚れた」


