「てんてこ舞い」、実は奥が深い?
忙しくてバタバタしているとき、「もうてんてこ舞いだよ!」なんて言ったことはありませんか?普段何気なく使っているこの「てんてこ舞い」という言葉ですが、実はちょっと面白い語源があるんです。
今回は「てんてこ舞い」の意味や語源について、わかりやすく解説していきます!最後までお読みいただくと、日本語についてちょっぴり物知りになれることでしょう。
「てんてこ舞い」とは

「てんてこ舞い」という言葉には、実は3つの意味があります。
- 何かに追われるように忙しく立ち回ること
- 嬉しくて小躍りする様子
- うろたえて大騒ぎすることや、あわてふためくこと
「喜んで小躍りする」という前向きな意味があるのは、ちょっと意外ですね。「てんてこ舞い」は漢字で「天手古舞」と書く場合もありますが、こちらは本来の意味とは関係ない当て字です。
「てんてこ舞い」の似た意味の言葉としては「てんやわんや」、「きりきり舞い」、「東奔西走」などがあります。
「てんてこ舞い」の語源

「てんてこ舞い(天手古舞)」には、2つの由来があると考えられています。
ひとつめは、「天手古(てんてこ)」が太鼓の音を表しているという説。祭囃子や里神楽で鳴り響く太鼓の音に合わせて踊る人たちの姿が、慌ただしく見えたことから、「てんてこ舞い」という表現が生まれたといわれています。
もうひとつの説は、祭りで山車や神輿を先導する女性たちの存在に由来するもの。女性たちは華やかな装いで舞い踊り、「手古舞(てこまい)」と呼ばれていました。この「手古舞」が変化し、「天手古舞」という言葉になったとも考えられています。
てんてこ舞いな状況に遭遇したら今回の雑学を思い出してみよう!

今回の雑学を振り返ってみましょう。
「てんてこ舞い」とは、忙しく動き回ること、喜んで小躍りすること、あわてて大騒ぎすることを意味する言葉です。普段は「忙しい」というニュアンスで使われることが多いですが、実は嬉しさを表す使い方もあります。
また、「天手古舞」と漢字で書くこともありますが、これは本来の意味とは関係ない当て字です。
語源には2つの説があり、ひとつは、祭囃子や里神楽の太鼓の音「てんてこ」に合わせて踊る様子が、慌ただしく見えたことに由来する説。もうひとつは、祭りで山車や神輿を先導して舞っていた女性たち「手古舞(てこまい)」の存在から転じたという説です。
似た意味を持つ言葉には、「てんやわんや」や「きりきり舞い」、「東奔西走」などがあります。
今回の雑学、てんてこ舞いなシチュエーションに遭遇したときにでも思い出してみてください。もしかすると、忙しさの負担がちょっぴり軽減するかもしれませんよ。
こんな記事も読まれています
 テレビを見ながら『ダンスを踊る赤ちゃん』が…0歳児とは思えない表現力が凄すぎると58万再生「頭抱えてるw」「癒し系ダンサー」
テレビを見ながら『ダンスを踊る赤ちゃん』が…0歳児とは思えない表現力が凄すぎると58万再生「頭抱えてるw」「癒し系ダンサー」
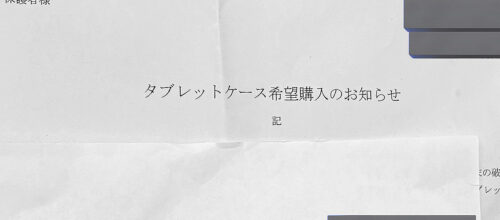 次男が学校からもらった『2枚の手紙』…プリントを出し忘れ”勝手に完結”した内容に爆笑の声「結果オーライw」と216万表示
次男が学校からもらった『2枚の手紙』…プリントを出し忘れ”勝手に完結”した内容に爆笑の声「結果オーライw」と216万表示

