4月26日は「よい風呂の日」!制定の理由とは

4月26日は「よい風呂の日」。テレビやSNSで目にすることが増えてきましたが、その由来を詳しく知っている人は案外少ないかもしれません。
私たちが毎日のように入るお風呂。その文化や意味を見つめ直すきっかけとして作られたのがこの記念日です。ただの語呂合わせにとどまらない「よい風呂の日」の背景には、日本人の心に根付いた入浴文化の奥深さがありました。
日本入浴協会が2022年に制定
「よい風呂の日」は、日本入浴協会が2022年に制定した記念日です。「よい(4)ふ(2)ろ(6)」という語呂合わせが由来になっています。
覚えやすく親しみやすいこの記念日は、日本記念日協会にも申請され、同年に正式に認定されました。比較的新しい記念日であるため、まだ広く知られていないかもしれません。
私自身もこの響きを初めて聞いたとき、「もっと前からあるのかな?」と思っていましたが、実際はつい最近の制定だと知って少し驚きました。それでも、この短期間で全国の銭湯やメディアにも取り上げられるようになり、「お風呂好き」な人たちの間では着実に浸透しつつあります。
「よい風呂の日」に込められた思い
「よい風呂の日」は、日本人の生活習慣としての「入浴」を再確認し、その価値を見直すために作られました。単に「体を洗う」だけでなく、「心と体をほぐす時間」としての入浴をもっと大切にしてほしいという願いが込められています。
さらに、日本入浴協会が掲げる目的の中には、「家族のコミュニケーションを深める場としてのお風呂」という視点もあります。子どもと一緒に湯船につかりながら会話をしたり、夫婦でゆったりとした時間を過ごしたり。お風呂は、忙しい日常の中で、自然と心の距離を縮められる貴重な場所なのです。
このように、「よい風呂の日」は単なる語呂合わせではなく、現代社会が忘れがちな“身近な豊かさ”を思い出させてくれる記念日でもあるのです。
日本のお風呂文化を外から見ると…

日本人にとってお風呂は当たり前の存在ですが、海外から見ると、その習慣はとてもユニークに映ります。文化を相対的に見ることで、私たちが当たり前だと思っていたお風呂の姿が、ぐっと鮮やかに見えてくるのです。
裸で湯船につかるという独自性
まず何より驚かれるのが、「みんなで裸になってお湯に入る」というスタイル。特に欧米諸国では、裸で人前に出ることに強い抵抗がある文化も多いため、日本の温泉や銭湯はカルチャーショックの対象になりやすいのです。
また、日本では42度前後の熱めのお湯を好む人が多いですが、海外ではぬるめ(38〜39度)のお湯が一般的。熱湯に平然とつかる日本人の姿を見て「まるで修行僧みたい」と表現されたこともあります。
こうした違いを知ると、日本のお風呂文化が“普通”ではなく、むしろ“特殊”であることに気づかされます。
入浴の時間と意味の深さ
海外では入浴時間が10分以内という国も珍しくありません。体を清潔にするという目的を果たしたら、それでおしまい。ところが日本では、30分以上かけてじっくりとお湯につかることが推奨されることも多く、そこに癒やしや“時間を楽しむ”という意味合いが加わっています。
単なる衛生行為にとどまらず、「心を整える時間」として入浴が定着していることこそ、日本人の美意識の表れなのかもしれません。
漫画『テルマエ・ロマエ』が描いた驚きと敬意
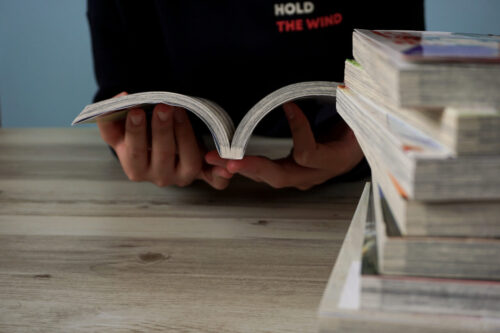
日本の入浴文化を面白く、わかりやすく世界に紹介した存在といえば、やはり漫画『テルマエ・ロマエ』でしょう。
この作品では、古代ローマの浴場設計士ルシウスが現代日本にタイムスリップし、銭湯や温泉、家庭風呂などに驚き、敬意を抱いていく様子が描かれます。読者はルシウスの目を通して、日本人には見えにくかった入浴文化の魅力を再発見することができます。
▶ローマ人が感動した“湯上がりの牛乳”
作中で特に印象的なのが、「湯上がりに飲む瓶入り牛乳」にルシウスが深く感動するシーン。私たちには当たり前のこの習慣も、彼にとっては「湯から上がった体にぴったりの滋養ある飲み物」として画期的に映ったのです。
▶テクノロジーも文化の一部
また、バスタブにお湯を自動で張るシステムや、追い焚き機能、温度設定、シャワートイレの存在など、日本の風呂まわりのテクノロジーにもルシウスは驚きっぱなし。これらの描写は笑いを誘いながらも、日本の“お風呂へのこだわり”が生活文化としてどれほど高く評価されうるかを証明しています。
よい風呂の日をきっかけに広がる楽しみ方

記念日とは、単なる「思い出す日」ではなく、行動を起こすきっかけにもなります。「よい風呂の日」も例外ではありません。この日を機に、お風呂がただの日課から、ちょっとした“体験”へと変わるのです。
話題になった“お風呂でアイス”の楽しみ方
ある銭湯では、「お風呂でアイスを食べよう」というイベントが開催され、大きな話題になりました。湯船につかりながらアイスを食べるという、一見アンバランスな行為が、体は温まりつつ口元はひんやりという絶妙なギャップで人気を集めたのです。
SNSでも「これはクセになる」「お風呂がテーマパークみたい」といった投稿が相次ぎ、イベントは大成功。五感を刺激する体験が、新しいお風呂の楽しみ方として受け入れられています。
銭湯で高級ヘアケアを無料体験
別の銭湯では、高品質なヘアケア製品を自由に試せるキャンペーンを実施。日頃の入浴が、ちょっとしたご褒美タイムに変わることで、銭湯の印象そのものがアップデートされました。
お風呂を“日常”から“非日常”に変えてくれるこうしたイベントは、世代や性別を問わず、身近なレジャーとしての入浴の価値を高めています。
歴史に見る“お風呂好き”な偉人たち

お風呂が日本人の暮らしに深く根付いていたことは、歴史をたどってみてもよくわかります。ここでは、お風呂をこよなく愛した偉人たちのエピソードをご紹介します。彼らの入浴スタイルからは、当時の文化や人となりが垣間見えてきます。
夏目漱石と“思考の湯”
明治の文豪・夏目漱石は、1日に2時間以上も湯船につかっていたとされています。彼にとって入浴は、体を清める行為以上に、「物思いにふける時間」でもありました。
静かなお湯の中で浮かんでくるアイデアを大切にしながら、『吾輩は猫である』など数々の作品を生み出したといわれています。現代でいえば、風呂が“ノートのない書斎”だったのかもしれません。
武田信玄と“戦場の湯治”
戦国時代の名将・武田信玄もまた、温泉を大切にしていた人物です。彼は信州(現在の長野県)の温泉地を訪れ、戦で疲れた体を癒やしたとされています。
中でも「下部温泉(しもべおんせん)」は特にお気に入りで、軍を率いたまま療養に訪れたことも記録に残っています。信玄にとって温泉は、身体を癒す場であると同時に、冷静な判断力を取り戻す静かな場所でもあったのでしょう。
お風呂は、癒やしだけでなく、人生の重要な場面にも密かに関わっていたのです。
生活がちょっと楽しくなるお風呂の豆知識

難しくないけれど「なるほど!」と思える雑学は、日々の会話をちょっと楽しくしてくれます。ここでは、身近なお風呂の中にある“知って得する”小ネタを紹介します。
お風呂の湯温が42度に落ち着く理由
銭湯や家庭のお風呂でも、「42度」が基準温度になっていることが多いですよね。実はこの温度、人が最も心地よいと感じるゾーンのひとつなのです。
体温より少し高い42度程度のお湯につかることで、副交感神経が刺激され、自然とリラックス状態に入っていきます。「なんとなく気持ちいい」の裏には、きちんとした生理的な理由があるのです。
アヒルのおもちゃはなぜ人気になったのか
お風呂といえば、あの黄色いアヒルのおもちゃ。今では世界中で親しまれていますが、実はそのルーツは1940年代のアメリカにあります。
爆発的に広まったきっかけは、ある子ども向けテレビ番組のワンシーンでした。楽しそうにお風呂で遊ぶ子どもの姿と一緒に映ったアヒルが視聴者の心をつかみ、あっという間に人気グッズへ。現在も、癒やしとユーモアの象徴として愛され続けています。
お風呂にちょこんと浮かぶアヒルは、単なるおもちゃを超えて、心をなごませる“演出”のひとつなのかもしれません。
お風呂の話を誰かとシェアしてみたくなったら
「お風呂の温度には意味がある」「文豪は湯船で思索していた」——そんな話を聞くと、つい誰かに話したくなりませんか?
今回紹介した内容は、どれも身近な話題でありながら、ちょっとした知識としても光るものばかりです。家族との食卓で、友達との雑談で、ふとした瞬間に「そういえば…」と披露してみてください。
知るだけで終わらず、話して、共有して、お風呂の魅力を広げていく。そんな一歩を、「よい風呂の日」から始めてみるのも、きっと悪くないはずです。
こんな記事も読まれています
 ディズニーランドの電気代はいくらぐらいなの?一般家庭の5万倍もの電力を消費していた!?
ディズニーランドの電気代はいくらぐらいなの?一般家庭の5万倍もの電力を消費していた!?
 ニコニコでご機嫌な『赤ちゃん』が…病院へ行った結果、表情の変化が面白可愛いと219万表示「ママ裏切ったな?の顔w」「ニヤけた」
ニコニコでご機嫌な『赤ちゃん』が…病院へ行った結果、表情の変化が面白可愛いと219万表示「ママ裏切ったな?の顔w」「ニヤけた」

